シビックプライドのまとめ(上地陽菜乃 227225D)
アムステルダム
要約
オランダの首都であるアムステルダムでは、近年都市間競争の激化、市場決定のスピードが速くなったことが原因で世界的文脈において徐々に低下していたポジショニングを明確にするために新しいブランド戦略・マーケティング戦略が必要とされてきた。
そこで行われた調査でアムステルダムの強みはクリエイティビティ、インベーション、商業精神であることが分かった。これらの分析からアムステルダムの未来のビジョンを共有していくモットーとしてI amsterdamという言葉が生まれた。
市民たちはこの言葉のコンセプトとブランドに誇りと自負心を持つようになり都市にさらなる愛着を持つようになった。
さらに、この言葉は著作権関係なくアムステルダムに住むどんな人でも使用することができるため市民一人一人を観光大使にさせるプロモーションとしての効果も発揮した。
このように現地に住む市民が都市に魅力を感じ続け、都市は市民を魅了し続けるという相互的な関係を築いていくことが都市のブランディングを成功させる上で重要である。
感想
I amsterdamを読んで、今まで都市を発展させるには広告の仕方を工夫したり、イベントを企画して人々を誘致したりといった方法しか思い浮かばなかったので言葉一つで都市に住む人々の意識を高め
、
都市ごとのブランド力を上げて発展していったアムステルダムのことを知ってモットーを制定するのは私にはなかった発想だと勉強になりました。
I amsterdamという言葉は人々と都市の繋がりをより一層強いものにし「都市を愛する心」をみんなが持つように働きかけていました。
このような意識を一人一人が持っているのなら今後もアムステルダムが発展していくことに人々も協力的になると思うのでこのモットーを作成したことは都市を発展させるための根本的な改革になったのではないかと感じました。
ハンブルグ
要約
ドイツ最大の港湾都市ハンブルグではMetropolis Hamburg―A Growing City(成長する都市ハンブルグ)というコンセプトのもと、大都市圏の成長力底上げのための政策を実行している。
中でも分断されていた港湾地区と市街地を再び結び付けようと「ハーフェンシティ」ではその活動が活発である。その一例としてまず挙げられるのが、開発順序のユニークさである。
ハーフェンシティでは建物や施設よりも先に広場などのオープンスペースが整備された。市民たちはオープンスペースのすぐ横で散歩やピクニックをしたりしながら建設の現場を目撃し続けるのである。
さらにハーフェンシティには情報発信基地として「インフォセンター」が建設された。そこでは開発プロジェクトに関する様々な情報公開が積極的に行われ、市民や来街者自らが情報を引き出せる体験ができるようになっている。
自分から獲得した情報は人に伝えたくなるという考えのもとデザインされたこの場所は市民同士、市民と街のコミュニケーションポイントとして活用されているのである。
感想
今回のハンブルグの文章に限らず、前回読んだアムステルダムの文章にも共通のすることだが、都市の成長計画を成功させるにはそこに住む人々が街に深くかかわれるような仕組みを作ることで大衆に関心と愛情を持つことが成功させる鍵となることが分かった。
ハンブルクのように街が成長していく様子を市民が情報を体験することや完成までの経過を見守っていくことでより都市と人との距離を縮めることができるというのは沖縄県でも取り入れることのできる仕組みなのではないかと感じた。
現に首里城は2026年の再建を目指しながら復興に向けた作業やイベントも行われている。しかし、自ら情報を引き出す体験できる機会であるイベントがあまり周知されていないように思う。
このイベントがもっと多くの人に知れ渡ることや、復興の様子を見守りながら県内の人々が交流できる場所があればハンブルグのような発展が見込めるのではないだろうか。
ブリストル
要約
イギリスの南西部に位置するブリストルはかつてイメージの弱い分かりにくい都市であった。
第二次世界大戦後復興で開発されたのが環状自動車道や郊外が主であり、中心市街地が分断されてしまっていたからである。
しかし、1990年前後になると、市と市民の価値観が自動車中心の街から歩いて楽しめる街に変化した。その時代に生まれたアイデアこそ「ブリストル・レジブル・シティ(わかりやすい都市)」である。
これは、街における様々なプロジェクトを交通と情報とアイデンティティによってつなぎ合わせ、総合的に都市をデザインしようとする挑戦である。
つなぐべきものがつながっておらずそれぞれを強調するだけだと、システムは分かりにくく、豊かな都市体験をすることが難しくなってしまう。
そこで情報をできるだけそぎ落としてシンプルにする、歩行者用の主要ルート計画「ブルールート」をはじめとするアートプログラムの配置などといった小規模なデザインを効果的に導入した結果、都市の体験を円滑なものにしたのである。
感想
観光客からしたら知らない土地だと情報が求められるけれど、その情報が互いに違うベクトルを向いていて、自己の存在感だけを主張するだけだと都市全体でみたときにバラバラに見えてしまって分かりにくい都市になってしまうという本文の内容に強く納得させられた。
確かに、知らない街を訪れることを考えた場合、街の中で使われる文字や色が統一されていたら記憶にも残りやすく観光体験の質を高めることができる。
また、様々なプロジェクトのつなぎ目をスムーズなものにする取り組みは地域住民の生活のしやすさにもつながるのではないかと思い、観光客の視点から見ても地域住民の視点から見てもプラスになるこのアイデアは素晴らしいものだと感じた。
ボルドー
要約
ボルドーはフランスの中でも観光地として目立つ存在感を放っていたが大掛かりな改革が行われることもなく80年代には都市機能は破綻をきたしていた。
しかし、1995年アラン・ジュペが新たな市長として就任したこと、EUの発足により都市再生の補助金を受けられるようになったことで都市再生の条件が整い始めた。
そこで行われたのが、市内の中心を流れるガロンヌ川沿いのフェンスを撤去し、都市の中に市民がくつろげる広場の確保と川の両岸の開発(2つの岸プロジェクト)である。
2つの岸のうち、左岸は歴史的建造物で彩った旧市街を有するエリア、右岸は全く新しい現代風の建物や庭園が立ち並ぶエリアで古と現代が川を挟んで対峙する。互いの河岸は開発された広場という公共空間により一体感を生み出している。
また、近年では広場にて川の祭り、ワイン祭りといったイベントも積極的に行われ、市民たちは何が自分たちの資産であるのかを意識する重要な機会となっている。
このように都市の中に市民がくつろげる場、楽しめる場を増やすことで市民と都市の距離が縮まり彼らは自らの都市を愛すようになるのである。
感想
今回、「ボルドー」を読んで印象に残った言葉は「ボルドーの都市再生の主役が市民であること」という言葉である。
やはり、都市レベルの改革・再生となるとその規模は非常に大きなものである。それなりに大きな改革を起こすには多くの人間が、変化の内容について納得して受け入れて、賛同してついてこない分には実現不可能だと思う。
その点で、改革の主体となる市民たちに対して言及しているこの言葉に非常に納得させられた。
ボルドーの川沿いに整備された広場のように多くの人々が親しみやすさを感じることができて、イベントを積極的に開くことでみんなが楽しむことができる場を設けることは市民参加型の都市活性化の政策として素晴らしいものだと感じた。
富山のLRT
要約
都市や地域では多くのグラフィックデザイナーが活躍しているが、大きな都市開発にはなかなか入り込めない現実がある。
しかし、富山県のLRTのデザインを行った島津氏は従来のデザイン業務から一歩踏み込み、地域にグラフィックデザインをデリバリーすることで市民が自身の街に誇りをもってもらうきっかけをつくれるのではないかと考えた。
市民には車両デザイン、愛称、市民協賛といった市民とデザインが関われる場を設け、企業には電停広告を一般的なものではなく、個性的なものにすることに対して同意してもらうことで結果的に企業価値を高めることに繋がった。
こうして市民と企業が積極的に参加したくなるトータルデザインの計画が進められていった。さらに、LTR開業後もイベントや季節のラッピングに多くの市民が参加できるような態勢が整えられている。
このような機会を設け参加意識を市民に持たせることが、デザインによるデリバリーへの共感を生み出し新たな地域の自慢と誇りに繋がっている。
感想
曾祖母の家の近所で、地元の小学生や地域の人が集まって川と歩道の境目の塀に絵を描いてデザインするという取り組みが行われているそうです。
祖母にきいてみると、この川では毎年こいのぼりの掲揚が行われたり、地元のハーリー祭りのようなイベントも行われたりと地元では愛されているスポットだそうです。
この文章を読んだとき、市民が街のデザインに参加している部分、街のデザインに参加したことで愛着がわいている部分、デザインの後もイベントなど交流の機会を作り続けている部分が共通していて、身近なところでもシビックプライドが垣間見えたことに感動しました。
私の中で、街にあるデザインされたものは、ほとんどが気づいたらそこにあったものです。しかしそれを自分が作り上げる手伝いをするとなると、その経験は思い出としてその人の中にずっと残ると思います。
今回の文章を読んで、自身との関わり度合いと街に対する愛情は比例関係にあるのだということが分かりました。
「理想の海外旅行」をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。
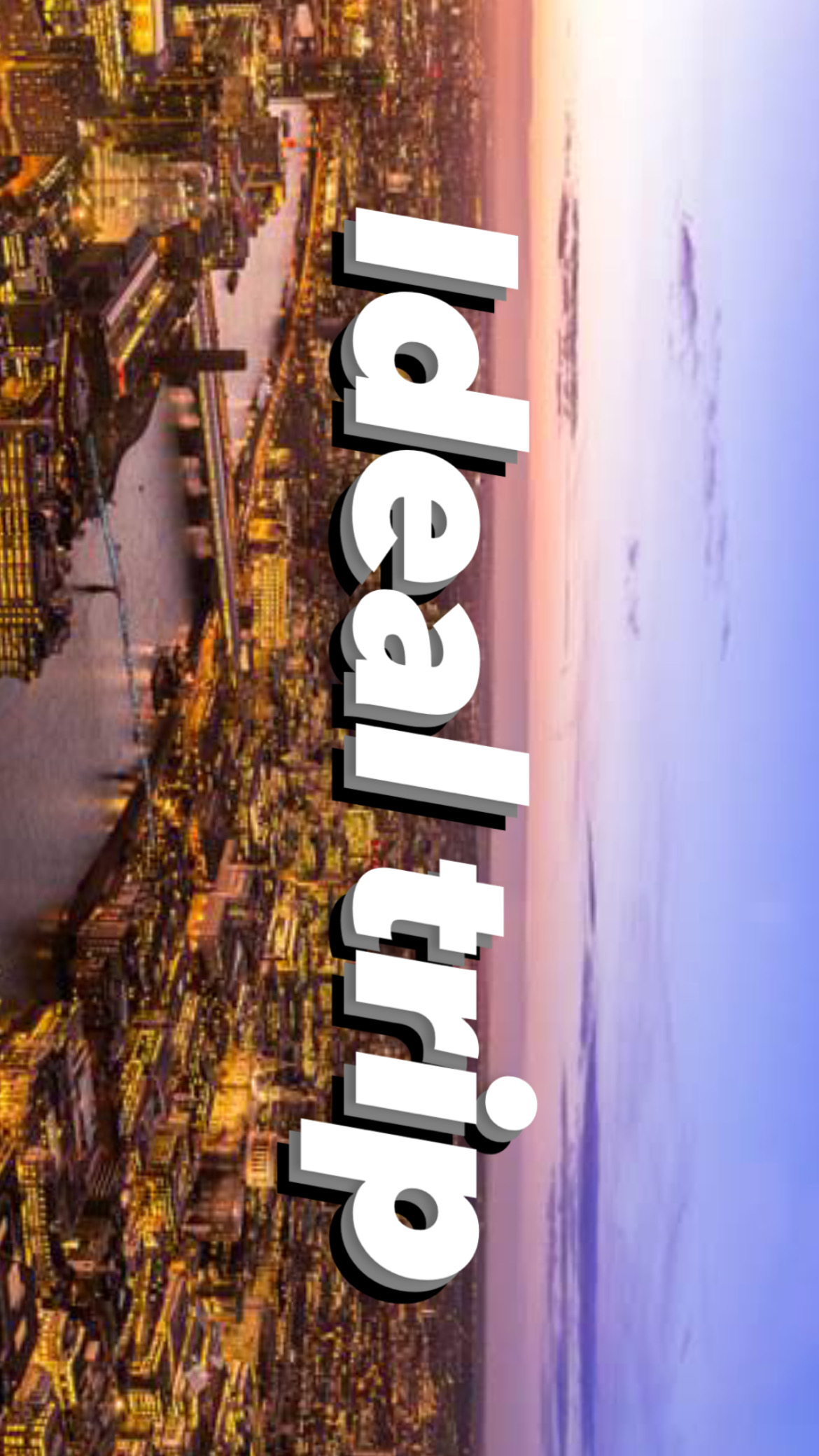
リンケージのまとめと感想はココ
 前のページへ戻る
前のページへ戻る
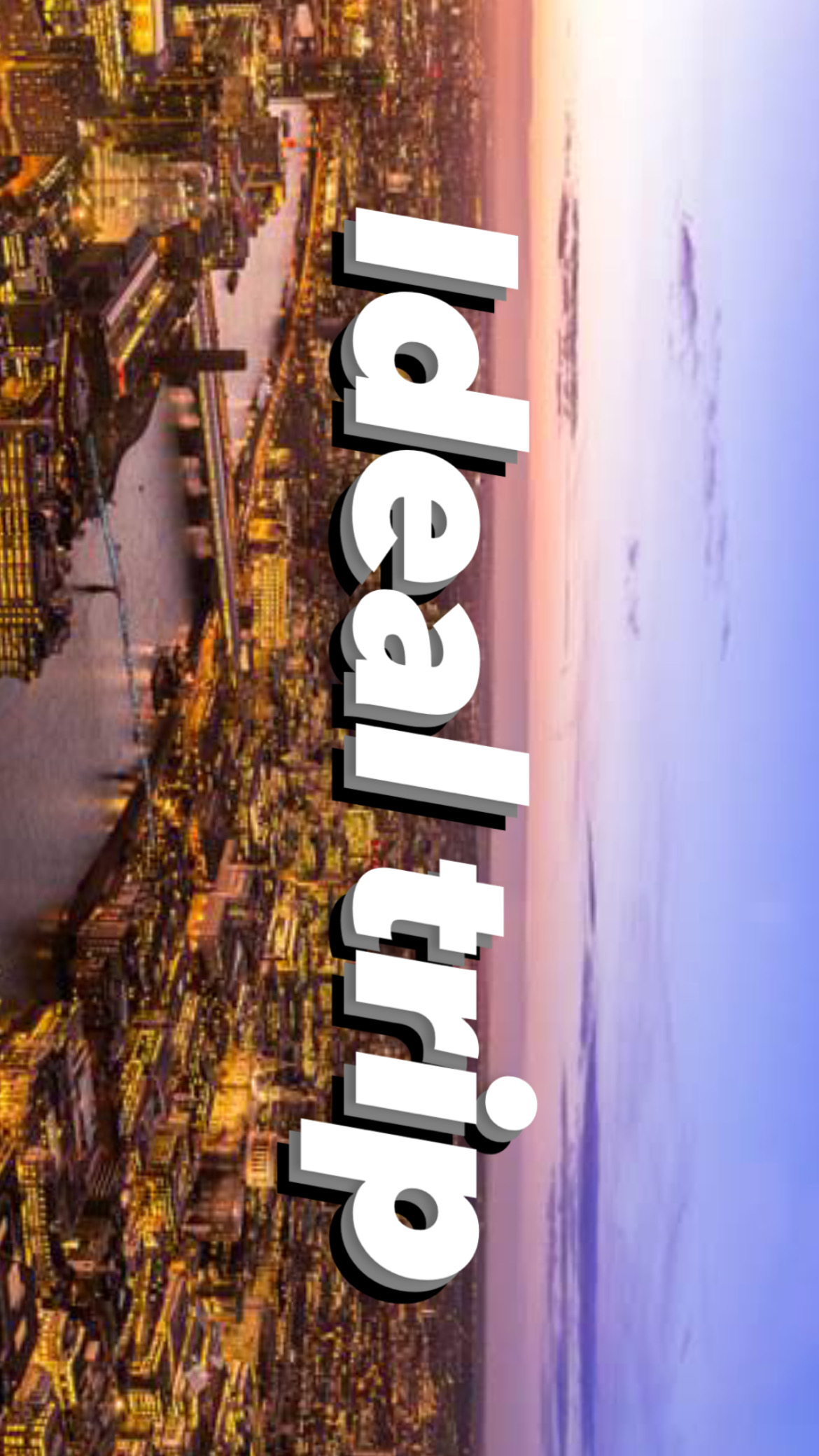
 前のページへ戻る
前のページへ戻る