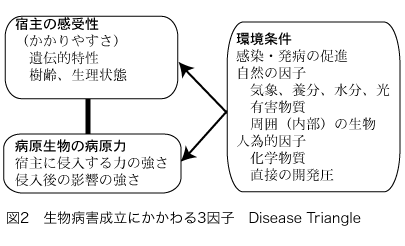森林病理学の到達点と展望
森林科学 forest science
森林病理学 forest pathology
流行病 epidemic diseases
病害の成立条件 disease triangle
持続可能性 sustainability
**著者
亀山 統一 KAMEYAMA, Norikazu 琉球大学・森林保護学
**はじめに
林学は,国家や王侯の財産たる林野の経営を目的に成立し,20世紀には産業と密着して発展してきた.しかし,今や森林とは営利的木材生産の場以上の存在であり,林学も林業学(forestry)から森林科学(forest
science)へと変貌している.森林生態系の保全と利用全体へと関心は拡大している.
**森林を視る目の変化
20世紀を通じて,森林の多様な生物は守られるべきとの認識が確立した.その根拠として,有用な未知の遺伝子資源が消失するのは損失だとする消極的視点や,それぞれの地域に成立した森林生態系はかけがえのない歴史的存在であり,その存続そのものが必須であるとの積極的視点があるが,森林保全の重視では一致している.
森林がもつ環境緩衝能力については,従来も,水源涵養や,土砂流出・崩落防止,防風防雪,海岸での飛砂飛塩・高波の緩和などの災害緩和機能が期待されてきた.現在は,これら局所的機能に加え,大規模な気候変動の防止に果たす役割など,地球規模の視点からの意義が強調されている.
樹木は光合成で固定した炭素を多量に樹幹に保持する.森林の樹木は,枯死すると分解されて二酸化炭素が放出されるが,その時には新たな個体がその場所で成長していく.森林が存続すると,全体として炭素が固定され続けるのである.大面積の森林が伐採されて再生しなければ,固定される炭素は減少し,逆に,裸地を修復して安定した森林にすると,その分固定される炭素が増大する.すなわち,地球温暖化の防止には,どこでも木を植えさえすれば寄与するものではないが,現存する森林の存続や荒地の再造林が不可欠である.
一方,木材は再生可能な物質・エネルギー資源であり,持続的社会の主軸となるべき天然資源である.石油・石炭と異なり,森林は,製品のリサイクルだけでなく,適切な経営により資源の再生も可能である.将来,エネルギー資源は太陽光や風力でまかなえても,依然"もの"をつくる原材料は必要である.利用すべき森林を定めて,構造材料や,紙・化学物質の原料,エネルギー源として樹木を利用することは不可欠である.持続可能な林業をそれぞれの地域で実現するという課題は一層重要になっている.
**森林病害とは
森林病理学(樹病学) 1)は,森林植物(主に樹木)の病害を研究する分野で,森林保護学の主柱の一つをなしている.森林植物の病害は,生物を病原とするもの(生物病害),温度・水分・土壌養分などの異常,大気汚染物質など環境要因で起こるもの(非生物病害),複数の微弱な因子が複合的に作用して生じるもの(森林衰退)がある.
非生物病害は,ある場所に例えばスギを植栽した場合,局所的な不適当な環境条件があると起こる病害である.あるいは,数十〜数百年に一度の異常現象で引き起こされることもある.前者の場合,造林をやめるか,その微環境に適合した樹種に転換するしかない.造林樹種(または品種)の生理的特徴と植林地の環境をよく把握して「適地適木」に努めることが本質的な対策である.後者は,農林業に不可避のリスクというしかない.
森林衰退は,現代の重要なテーマであるが,低濃度の汚染物質や気象変動が広域に影響し,また,開発行為が森林にまで影響を及ぼした段階で初めて被害が顕在化したものである.現状でもその具体的な解明には限界がある.例えば,日本産樹木は低濃度の大気汚染物質を長期に与えても,外見上も解剖学的にも明瞭な病理症状を示さず,従来の研究手法では樹体に起こる変化を追跡できない.そうした微弱な因子も複合すると衰弱や枯死させうることを示すには新たな手法が必要である.
一方で,生物病害は,ある樹種に広い範囲で激甚な被害を及ぼすことがあり,病原微生物の研究手法も早期に開発されてきた.農作物では,19世紀のアイルランドにおけるジャガイモ疫病の大流行,稲のいもち病などが有名だが,森林にも社会に大きな影響を及ぼす流行病がある.
**20世紀の主要な流行病
クリ胴枯病(chestnut blight)は,米国のクリをほぼ絶滅させた.クリは優良な用材樹種であり,クリ材が日本でも古代の遺構から発掘されるなど,利用の歴史も古い.北米でも貴重な広葉樹有用材であったが,1904年から突如として成木が急激に死に至る病害が発生して,40年間で合衆国中東部を中心に分布していたクリはほぼ全滅し,1938年には欧州にも入って被害を与えた.この流行病の病原は,カビの一種Cryphonectria
parasiticaである.この菌は,東アジアに普通に分布し,日本や朝鮮半島,中国産のクリでは発病せず,樹皮の中で生活して,樹勢の衰えたときに生きた組織をわずかに侵す菌である.ところが,種の異なるアメリカグリでは劇的に幹枝の組織を侵してしまう.
現在では,米国での本病の大流行は,日本からの病原に起因することが分かっている.アメリカグリ(宿主)と胴枯病菌(病原)の間には,接触する機会がなく,宿主を殺さない程度に病原が寄生生活するという相互関係が発達せず,たまたま強力な病原性を発揮してしまったのである.古花粉学の研究から,有史以前にもクリ胴枯病がアジアからアメリカに渡って植物相に大きな影響を与えたらしいことが示唆されている.しかし,流通の国際化の進展に伴って,こうした流行病の出現する危険が飛躍的に高まっている.
ニレ立枯病(Dutch elm disease)は,欧州で突如発生し,米国・カナダにも持ち込まれた病害で,今も被害を生じている
2).五葉松発疹さび病(white pine blister rust)も,ユーラシア大陸の五葉松類に緩やかな被害を出していたが,欧州と米国の造林地に侵入して劇的な流行を示した病害である.逆に,米国のセコイアにつく菌が日本に入って,スギ苗を劇的に死滅させたスギ赤枯病の事例もあるが,この病害は,効果的な苗畑での農薬散布法が早期に確立し,制圧された.
**マツ類材線虫病
今,世界的に深刻な森林病害はマツ類材線虫病である.「松くい虫被害」として知られる本病は,20世紀初頭に米国から侵入し,日本の松林に激害を与えてきた.戦後,本病被害が拡大する中で膨大な研究が行われた.病原がマツノザイセンチュウ(Bursaphelenchus
xylophilus, 以下材線虫)という線虫とわかったのは,1970年である.
植物寄生性の線虫は,一般に土壌中に生息して根に加害する.根菜類への被害や,連作障害の原因として農業では着目されてきたが,樹木の成木の成長に影響する線虫は知られていなかった.まして,材線虫はマツの材(木部)中で生活し,幹での水の移動を阻害して枯死させるという,植物病理学の常識外の生態をもっており,長い間見落とされてきた.被害木の材中に線虫を見出した清原と徳重が,あえて培養,接種を試みて強い病原性を確認し,本病病原と判明したのである
3).
本病は,材線虫が健全なアカマツ,クロマツ,リュウキュウマツなどの若い枝の傷口から侵入することから始まる(図1).材線虫は枝の表面から木部に移動し,幹で大増殖してマツの仮導管(針葉樹は導管をもたない)の水分通道機能を破壊するのである.マツは感染から数ヶ月で全身の葉が赤変して枯れる.水分通道阻害が枯死原因なので,夏場の高温,小雨,強風など乾燥した気象条件下で,本病の進行は促進される.
枯死したマツの材には菌類が侵入する.材線虫は植物も菌も餌とするので,今度は侵入した菌糸を食べて増殖する.枯死木にはさまざまな昆虫も侵入する.その一つ,マツノマダラカミキリ(Monochamus
alternatus)は枯死したマツの幹に産卵し,幼虫・蛹の時代を材中で過ごす.これが,体のある部分に材線虫を大量に付着させて,翌春に羽化脱出するのである.成虫は健全なマツの若い枝を食べ,このときに体から材線虫が落下して傷口から新たな感染が起こる.
材線虫は米国に土着の種とわかり,北米のマツ類にはほとんど病原性を示さない.本病も,外国由来の新病原により突発した流行病(侵入病害)であった.本病は,日本から台湾,朝鮮半島,中国大陸にも上陸して,大規模な流行を引き起こしている.また,欧州産のマツも本病に罹ることが知られ,近年ポルトガルでも被害が発生し,欧州各国は厳重な防疫態勢を敷いている
4)
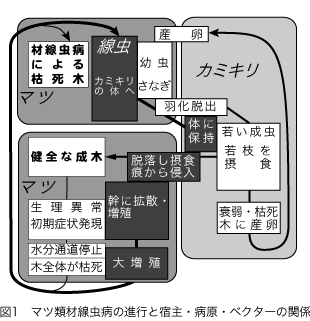 .
.
**材線虫病の成果と課題
マツ材線虫病に関する日本の研究は,森林病理学史上特筆される成果である.森林病害について,病原,宿主,ベクター(病原の運び屋),非生物・生物を問わず環境条件,防除方法について,本病ほど総合的に研究された例は少ない.材線虫が水分通道を阻害する具体的機構が未だ明らかでないなど,今後の課題も多いが,これまでの研究を通じて,森林植物と病原生物の関係についての知見や研究方法は大きく前進した.そのことを評価した上で,問題点を3点指摘したい.
第1に,研究成果の普及の弱さである.材線虫病は科学的にも興味深く,防除をめぐる社会的関心も大きいテーマであるのに,研究者集団による市民への普及活動は不十分である.日本で森林病理学を専攻できる大学は実に少ないうえ,市民や学生が手にして読める出版物がほとんどないため,本病について多くの人々が知る機会は乏しい.
実は,このことは研究者にもあてはまり,本病研究の初期の論文の多くは日本語で書かれ,海外の研究者の参入が難しかった.若手や異分野から本病研究に加わるにも困難がつきまとった.幸い,岸によって,2,300編余の論文・調査報告を包括するレビューが出版される
5)など,研究者の成果の共有は大きく進んでいる.
第2に,成果の行政への反映がお粗末であった.本病防除のため,伐倒駆除(被害木を伐り倒し材を焼却する)と農薬散布(カミキリムシの忌避や密度低下のために,羽化脱出時期にマツ若枝に殺虫剤を散布する)が,高額の国費や自治体予算を投入して精力的に行われた.しかし,事業の実態は研究成果が活かされたものとは言えない.
マツが分布するまとまった地域で,伐倒駆除と(可能な場合には)農薬散布とを組み合わせて,数年間継続して防除を行えば,本病被害はほぼ制圧できる.しかし,予算の計上が遅れたり不足すると,駆除作業の時期が遅れたり,被害木の一部が放置されるため,効果は激減する.また,農薬散布はその後の伐倒駆除を併用して初めて大きな効果が期待できるのだが,安易な農薬依存や,不適切な場所・方法での散布もままあった.一方,ある地域で本病を制圧できても,再侵入がないように,不要なマツ林を他の樹種に転換して伝播経路を絶ち,守るべきマツ林を孤立させる政策も必要である.それらが十分考慮されなかった.
また,適切な調査を経ないまま,"マツが枯れれば材線虫病"などと安易な判断を行政がするならば,本病以外のマツの枯死要因を見落とすことにもなる.これらが,本病の知識の普及不足と相まって,「防除対策は効果がない」「材線虫は病原でない」などの誤った認識を生む温床をつくってしまった.抜本的な是正が必要である.
第3に,本病被害が国際化し,また,研究方法の発展もめざましい現在,より学際的,総合的な本病研究が必要である.すでに,こうした議論は学会でもインターネット上でも行われ,国際会議も開かれている.しかし,独法化の進行する現在,国の研究機関などでは本病研究の推進が困難な雰囲気ともいわれる.長期間を要する困難で地道な研究も,国の経済力にふさわしく可能にするような科学政策こそが必要である.
以上のように,流行病の発生原因とその対策は社会的な要素と不可分である.森林生態系保全のために,流行病対策の必要は重みを増している.
**病害発生の3因子 −進む具体的解明ー
森林病害を考えるとき,宿主,病原とそれをめぐる環境の三者と,その相互関係(disease
triangle 図2)について知ることが必要である.上述の流行病は,病原の力が突出して強い例であるが,この場合は,放置すれば宿主の樹種を絶滅させて病害そのものが消失するか,たまたまその病害に抵抗性のある数少ない個体が生き残って繁殖し,その後は弱い病害として推移する.おおかたの病害は,ある範囲の環境条件下に宿主植物や病原がおかれた場合に現れるものである.
すると,天然林では,病害とは,衰退した樹木の枯死や遺体の分解(腐朽)により世代の交代を促進し,森林を若く健康に保つ働きをしていると考えることもできる.また,ある病害の顕著な発生は,その森林へ異常な環境負荷がかかっていることを知る指標ともなりうる.木材生産だけでなく,森林生態系の理解や保全管理にも,病害研究は必須である.
森林では,非常に複雑な環境要因が個々の樹木の生育履歴に影響を与えており,その過程で病気が起こる.病原微生物の感染から発病・進展には数年以上を要することもある.したがって,森林の樹木のdisease
triangleの分析と再現は容易でない.しかし,近年の科学・技術の発展は,森林病理学研究にも大きな変革をもたらしている.
微生物の種同定やクローン(菌類では「個体」の概念の適用は難しい)の識別は,しばしば非常に困難である.樹木病害の病原は菌類が多いが,菌類の体の構造は単純で,生殖構造がないと種も同定できない.ところが,実験室で培養して生殖構造(子実体,キノコなど胞子を作るもの)をつくらせることが難しい菌種も多い.同種の菌でのクローンの識別はさらに困難である.これまでは,名人芸的な培養技術で,菌株の交配試験を行ったり,子実体をつくらせて研究してきたのである.だが,DNA分析の進展により,容易に菌の種同定やクローン識別を行える可能性が生まれた.
これは,森林生態系における微生物の生活をより深く知る道具となりうる.例えば,材質腐朽菌(樹木の材を分解するサルノコシカケの仲間など)は森林の物質循環の重要部分を担っているが,材や土壌中でどのように生活しているかはよく知られていない.また,ほとんどの植物では,細根にある種の菌類が付着して,菌根という独特の構造をつくることが知られている.菌根をつくる菌根菌は,菌糸を土壌中に広範囲に伸ばして水分や無機養分を取り込むことができ,菌根において,植物はこの養分や水分の一部を菌から奪い,菌根菌は植物の光合成産物の一部を利用していると考えられている.このような,腐朽菌や菌根菌の働きの解明も,大きく発展しつつある.
一方,著者は,マングローブ植物に病害をもたらす寄生菌類の研究を進めている.日本でマングローブが用材生産などの経済価値を持つことはないが,マングローブのような特殊な森林生態系の植物寄生菌類にも研究が及んでいる.海水と淡水が交錯する厳しい環境変動を伴う条件下でも,植物と寄生菌の相互関係が成立しているのである.
また,植物に内在するが,必ずしも病害を引き起こさない菌類の研究も進展しつつある 6).
ところで,森林の樹木の方を診断するには,継続的観察のために,伐り倒さずに植物や環境の状態を測定する手法が必要である.病理解剖や病原の分離には病患部を切り取るほかないが,植物にかかる環境負荷(ストレス)は,従来,植物組織の浸透圧(正確には水ポテンシャル)の測定値からある程度把握していた.それが,水分ストレスがかかったときに導管・仮導管中を上がる水柱が切れる微細な音を測定する方法(AE法)が開発され,材線虫病の研究などで,植物の水分状態の変化が精密に追跡されている.あるいは,植物はストレスがかかるとエチレンを産生することが知られるが,植物の放出するエチレンの精密な定量から樹体のストレス状態を推定する方法も試みられている.植物の受ける環境負荷を測定する手法も,次々拡大しているのである.
多様な森林において,地上・地下部で密かに活躍している微生物の働きや,それへの環境の影響が明らかにされていくにつれて,森林生態系の概念は大きく塗り替えられていくだろう.森林における菌類の生活や,環境因子の植物や菌類への作用の解明は,生態系保全の基礎となる.例えば,大気汚染物質の低濃度で長期間の被曝などが複合的に作用して発生すると考えられている森林衰退問題についても,原因究明や対策のための指針が与えられることになるだろう.
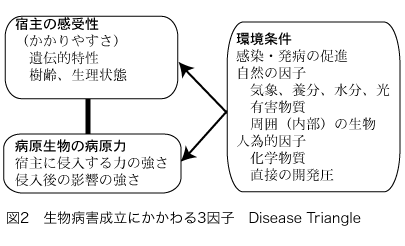
**おわりに
著者が初めて取り組んだ樹木病害は,ヒノキの篩部や形成層に局所的な不全を生じるヒノキ漏脂病である.20世紀初めから原因不明であったこととヒノキの篩部の構造の美しさが,卒論研究に選んだ理由だったが,この素朴な動機は5年間,研究の原動力でありつづけた.現職に就いて,ついに病原菌発見の報に接して感動がやまなかった.しかし,著者は今も,漏脂病は発見された病原の加害だけでは説明できないと考え,研究の推移を見守っている.また,材線虫病が樹木と水の関係を探る糸口であるように,漏脂病は,形成層や篩部の働きを知る好材料であり,興味はつきない.
一方,新たな流行病の懸念は,本土の広域で,カシノナガキクイムシの大量加害と新種の菌類の関与を伴うナラ・カシ類の集団枯損が発生していることで,現実のものとなっている.
森林病理学は,突発する流行病とのたたかいのように優れて応用研究であるとともに,原因不明の病害や衰退,見過ごされてきた菌類の働きをめぐる静かな基礎科学の営みである.著者も若手の一人として多くの仲間と切磋琢磨したいし,多様な分野の研究者と共同して研究の視野や手法を革新したい.それに値する魅力的な分野である.
**文献など
1) 概説書に,小林享夫ら(1986)新編樹病学概論.養賢堂; 真宮靖治ら(1992)森林保護学.文永堂出版;
鈴木和夫ら(1999)樹木医学.朝倉書店.など.
2) 世界科連国際シンポ(本誌35(12)33-37参照)に参加した際に会ったカナダ・レジャイナ市当局者は,著者がforest
pathologistと知るや,Oh! Dutch elm disease! と言った
3) 清原友也・徳重陽山(1971)日本林学会誌53,210-218.
4) 佐藤ら(2000)樹木医学研究4,19-22.
5) 岸洋一(1988)マツ材線虫病 -松くい虫-精説.トーマスカンパニー; Kishi, Y.(1995)The pine
wood nematode and the Japanese pine sawyer. Thomas Company, Tokyo.
6) 普及書に,金子繁・佐橋憲生(1998)ブナ林をはぐくむ菌類.文一総合出版.など.
ホームへ
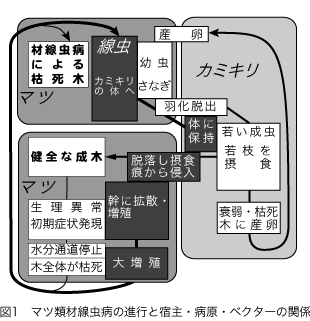 .
.