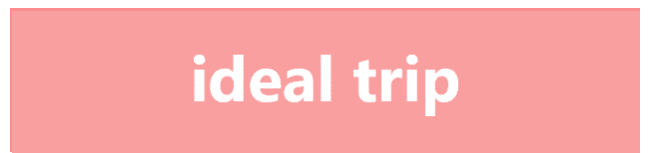アムステルダムでは、「I amsterdam」というロゴを中心としたコミュニケーションが存在し、街のあらゆる場面でそのロゴが見られる。2004年、新たな都市マーケティングとビジョンの策定・そのビジョンを人々に伝えるブランドキャリアの必要性が提言された結果、「アムステルダム・パートナーズ」の設立と「I amsterdam」キャンペーンが誕生した。「I amsterdam」は「人がアムステルダムをつくる」というコンセプトのもと実施された都市マーケティングプロモーション戦略のモットーである。クリエイティビティ・イノベーション・商業精神という都市の価値を浸透させるには、人々の都市に対する愛着と自負が強い力となる。「I amsterdam」は市民一人ひとりの「アムステルダム精神」を引き起こし、都市と人々とのビジョンの共有、そしてアムステルダムの魅力のアウトプットに繋がっている。ロゴを中心としたコミュニケーションは都市と人を結び、都市と市民が一体となった都市マーケティングを可能としている。
都市マーケティングのプロモーション活動として、ロゴを用いてコミュニケーションを図るという斬新なアイデアが印象に残った。一見単純に見えるキャンペーンが、都市のマーケティング活動において重要な役割を担っていることに意外性を感じたからだ。本文に「ブランディングが成功している都市の人々は都市に対する自負や愛着を持っている」とあるが、アムステルダムは「I amsterdam」というシンプルで明確なコミュニケーション戦略がその事を可能としていることが分かった。「都市の資産は人」という考え方は都市と人々の間に一体感を持たせ、結果として都市の魅力のアウトプットに繋がっていることから、社会の構築には人ひとりひとりの存在が重要であると感じた。
ドイツ最大の港湾都市ハンブルクでは、「ハーフエンシティ」の開発というヨーロッパ最大規模の都市再生プロジェクトが行われている。都市再生と市民の関係構築をモットーとしたその開発では、開発の初期段階で公共空間を整備することで開発の段階から市民と地区との接点を生みだした。そして「インフォセンター」と呼ばれるコミュニケーションポイントの設置というアイディアがハーフエンシティの開発には存在する。インフォセンターを設置し積極的に情報開示が行うことにより市民や来街者との情報共有が可能となった。そこでは、主に開発の全貌が可視化できる巨大都市模型の作成や、地域の計画や歴史の展示、開発現場見学ツアーやディスカッションの実施が行われている。
「インフォセンター」という街と市民が相互にコミュニケーションを図れる存在をつくることで、市民に見守られながら街は開発され、またその街は市民のものとして発展していく。
ハンブルクの「ハーフエンシティ・インフォセンター」のような情報開示を行うコミュニケーション・ポイントの設置は都市と市民の密接な関係を構築する上で非常に重要あることが分かった。沖縄県においては、首里城が「ハーフエンシティ・インフォセンター」のような役割を担えるのではないか。那覇市首里には、「首里杜地区」という首里城を中核する地区があり、歴史まちづくり計画が行われている。そこで、首里城を観光名所としての立ち位置だけではなく、「インフォセンター」として地区の人々の集まりの場として対話、情報交換ができる場にすることが求められると考える。
このように、地区と市民とのコミュニケーションが積極的に行われることで、市民の自分の住む地域に対しての自負が芽生えるのではないか。
「ブリストル・レジブル・シティ」は、公共空間の整備に連動したサインやマップのデザイン、情報デザインによる都市イメージの統合、アート・プロジェクトよる場所の感覚の強化を行うなど、トータルに都市をデザインするプロジェクトである。ブリストルは元々、戦後復興で進んだ中心市街地の分断によって分かりにくく歩行者に不親切な都市であった。しかし、1990年前後に現れ始めた中心市街地や文化・産業面などの変化に伴って「ブリストル・レジブル・シティ」のアイデアは生まれた。このプロジェクトは「連結・結合」「アイデンティティ」「戦略的都市マーケティング」という都市のイメージ強化に関連するテーマが設定されている。都市で起こる開発や活動の断片をつなぎ合わせ、都市全体を統合することによって人々の都市体験そのものを都市の情報としている。こうした総合的で円滑な都市体験が、都市と人とのコミュニケーションを可能にしている。
「ブリストル・レジブル・シティ」では、まちのあらゆるプロジェクトをつなぎ、都市をトータルでデザインすることで「分かりやすいまち」を作り出していることが分かった。特に、プロジェクトの実行にあたってまちのイメージカラーやオリジナルのフォントの設定や、路上マップとサインシステムの設置場所を「ブルールート(歩行者用の主要ルート)」に絞るという工夫は「分かりやすさ」を与える上で重要なポイントだと感じた。沖縄県内各地で見られる案内標識のデザインには統一性がなく、またマップにおいても分かりづらさを感じる。そこで、ブリストルのように都市を包括的にデザインすることはこれからの沖縄の観光において重要になっていくのではないか。
ボルドーは、キリスト教聖地へ続く巡礼路の拠点の一つであり、18世紀の壮麗な街区や教会もあることから、フランス内でも際立った観光地であった。そのため大がかりなまちづくりが行われてこなかったが、アラン・ジュペの市長就任をきっかけに、「市民に開かれた公共空間」のせ整備が行われ始めた。かつてのボルドーの繁栄の象徴であったガロンヌ川を中心に据えた河岸開発である。まちの歴史の象徴ともいえる川辺が市民の憩いの空間としてオープンし、公共空間再編と連動して中心市街地の歩行者空間が整備された。まちの「アイデンティティ」と「アクティビティ」を結ぶ結節点として、歴史的資産を十分に活かすための公共空間整備は役立っている。歴史と現代が融合する美しい都市風景や誰もが憩える公共空間の整備は、都市・建築センター「アルカン・レーヴ」による展示やフェスティバルなどを通して市民に周知された。こうしたまちの心の支柱に人々は誇りを感じている。
かつての都市の繁栄の象徴であった場所(ボルドーではガロンヌ川)をまちの求心力としての公共空間としての都市開発があるということを学んだ。まちの歴史の象徴である場所を市民の憩いの空間としてオープンすることによって、歴史と市民の接点をも作り出していると感じた。また、都市開発を行っても市民への周知が十分でなければ意味がない。そこで、ボルドーのように歴史と現代が融合する都市風景や公共空間の整備を周知するために、展示やフェスティバルを開催することは非常に重要である。「開発の主人公は市民である」ということを念頭にした都市開発、そしてそれを周知するための活動はこれからのまちづくりにおいて欠かせない要素だと感じる。
富山県富山市は、LRTのトータルデザインという地域の取り組みにグラフィックデザインをデリバリーし、また都市のグラフィックデザインに市民参加の仕掛けを作ることで市民にシビックプライド(自分たちのまちに対する誇り)をもたせることを目指したまちである。「TOYAMA クリエイティブライフ」は富山ライトレールのトータルデザインのコンセプトであり、以下の3つの目標を表す言葉として設定された。1つは、「高齢化社会や環境に配慮した住みよいまちづくりの実現」、次に「まちづくりと連携した、富山の新しい生活価値や風景の創造」、そして「世界に向けて富山市民が誇れるような路線づくり」である。富山ライトレールのトータルデザインでは「快適性、地域性」「先進性」「情報発信」の3つの尺度から対象物のデザインが行われている。また、LRTのまちづくりに対して市民の具体的な参加意識が生まれることで多くの市民サポーターや新たな地域の自慢と誇りに繋がっている。
富山市で行われたライトレールのトータルデザインの中で、「ラッピング車両によるデリバリー作戦」が特に印象に残った。ラッピング車両は富山ライトレール開業時からイベントや季節ごとに行われている。そこで、ラッピング車両の装飾に幼稚園児から高校生、主婦層まで多くの市民が関わっている点がポイントであると感じた。なぜなら、年齢層を問わず市民全体を巻き込んだまちづくりはまちの魅力を発信するための循環が生まれていると考えるからだ。まず、市民に全面に出てもらう取り組みを行うことで市民のまちの対する帰属意識は高まり、次にメディアなどの外部の目に留まることでまちの魅力が発信される。このことからまちづくりにおける市民参加の形の重要性が窺える。
「観光リンケージのまとめ」をご覧になりたい方はココ